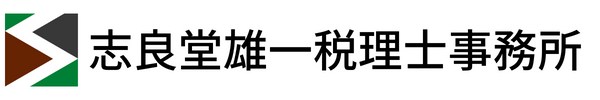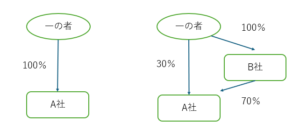成年後見制度について
最近、弁護士の先生や司法書士の先生と一緒に相続に関するセミナーをすることがあり、相続税以外のことについても学ぶことが多いです。
今回は成年後見制度についてまとめました。
成年後見制度とは
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)は、高齢や障害、病気などによって判断能力が不十分な人を法的に支援するための制度です。本人の財産や生活、法律行為を適切に管理し、本人の利益を守ることを目的としています。本人の判断能力の程度に応じて、以下の3つの類型があります。
補助人
判断能力が一部不十分な人(被補助人)を支援するために設定されます。補助人の役割は、被補助人の生活や財産管理をサポートすることで、本人の自立を最大限に尊重しつつ、必要な範囲で支援を行います。他の後見制度と比較すると、補助人の権限は最も限定的です。
家庭裁判所の審判で定められた範囲内で、被保佐人が法律行為を行う際の同意権、特定の行為について代理権、被補助人が補助人の同意を得ずに行った法律行為の取消権などを有します。
保佐人
判断能力が著しく不十分な人(被保佐人)を支援するために設定されており、被保佐人の重要な法律行為について同意や代理を行う権限を持ちます。ただし、成年後見人に比べて権限は限定的で、被保佐人が基本的には自分で法律行為を行うことを前提としています。
被保佐人が特定の法律行為を行う際の同意権、特定の行為についての代理権、被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った法律行為の取消権などを有します。
成年後見人
判断能力を欠いている状態の人(被後見人)の財産や生活を適切に管理し、本人の権利を守るために広範囲に及びます。ただし、後見人の行動は家庭裁判所の監督下で行われ、不正や濫用が防止される仕組みになっています。
被後見人の財産管理権、被後見人に代わって契約を行う代理権、被後見人が成年後見人の同意を得ずに行った法律行為の取消権、医療や介護サービスの利用手続きなどの身上監護権などを有します。
成年後見制度の利用手続き
本人やその家族、福祉関係者が家庭裁判所への申し立てを行い、家庭裁判所が後見人、保佐人、補助人を選任します。親族のほか、弁護士や司法書士などの専門家後見人などが担います。
この制度の短所としては、①やめられない、②流動的な財産活用ができない(贈与など)、③成年後見人等の費用などがあげられます。
まとめ
上記のように、非常に専門的、法律的な話になります。また一度始めたらやめられない制度でもあります。
成年後見制度を検討する際には、専門家や地域の相談窓口で具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。